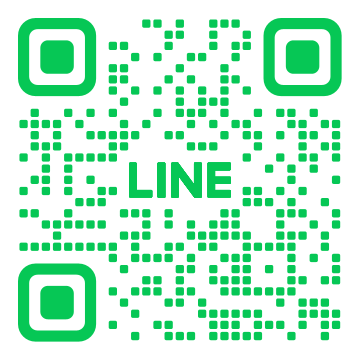湿度60%を超えるとニオイは“増える”のか“感じやすくなる”のか
結論
多くの現場では、臭気源そのものが一気に“増える”のではなく、湿度が60%を超えると「感じやすさ」が跳ね上がることが主因です。理由は①素材からの再放散、②微生物の二次臭、③人側の嗅覚感度の3つが同時に効くため。したがって、除湿は立派な消臭手段になり得ます。
なぜ感じやすくなるのか(3つの視点)
- 再放散(素材側):布・紙・木は湿気で内部に“水の橋”が生まれ、付着していたニオイ分子が気相へ戻りやすくなります。ソファやカーペット、壁紙裏の紙層が典型です。
- 二次臭(微生物):相対湿度60%前後からカビ・細菌の代謝が進み、酸っぱい・カビっぽい・土臭い系の成分が増えがち。台所の布巾、排水口周り、玄関マットは“湿って温い”条件が揃い、においの加速装置になりやすい場所です。
- 感じやすさ(人側):高湿度は鼻粘膜を潤し、同濃度でも強く感じることがあります。さらに湿気で空気が重く停滞し、においの滞留時間が伸びて体感が上がります。
注意(NGパターン)
芳香剤で上書きすると、高湿度下では香り+元臭が“合算”され、かえって不快度が上がり、苦情が長期化することがあります。原因除去→中和→吸着→香りの順を崩さないのが鉄則です。
まとめ
“暑さは温度”、“においは湿度の境目”。まず60%の壁を下回るまで除湿し、軽くなればそのまま運用、変わらなければ源を断つ。この順で無駄な工事や薬剤投入を減らせます。